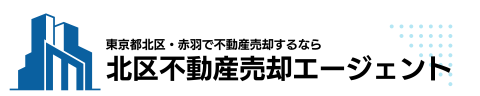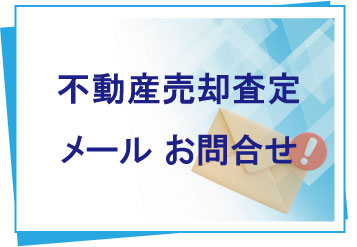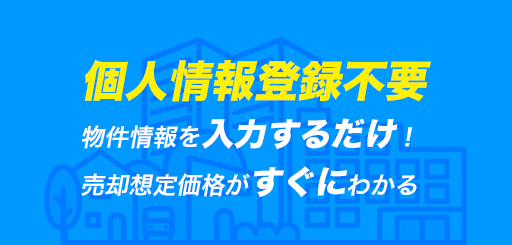建築基準法改正でリフォームにも建築確認申請が必要?
建築基準法改正とリフォームにおける確認申請

2025年4月に建築基準法が改正されました。この改正によって、今までは建築確認申請(以下「確認申請」)が不要だった木造2階建住宅などでも、大規模なリフォームや構造に関わる工事を行う場合には確認申請が必要になりました。特に「新2号(建築基準法第6条第1項第2号)建築物」に該当する住宅では、フルリフォームやスケルトンリフォームなどの際には確認申請の義務が生じます。
建築基準法改正とリフォームにおける確認申請の必要性 〜2025年改正のポイント〜
リフォームは「住まいを快適にするための工事」として広く行われていますが、2025年4月に施行された建築基準法の改正により、その位置づけが大きく変わりました。これまで「小規模な木造住宅は確認申請不要」とされていたケースでも、一定の条件下では確認申請が必要になります。改正の背景と具体的にどのようなリフォームで確認申請が必要になるのかを整理します。
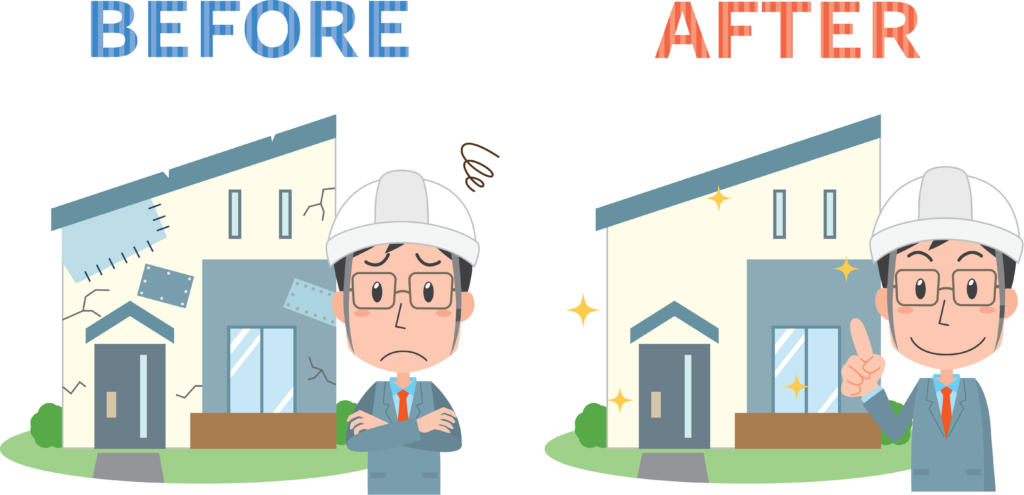
【改正の背景】
• 安全性の確保
リフォーム需要の増加に伴って、構造的な不具合や耐震性不足が社会問題になりました。
• 省エネ・脱炭素社会の推進
住宅の省エネ性能を高めるため、改修時にも基準適合を求める方向になってきました。
• 法的整合性の明確化
今まで曖昧だった「リフォーム時の確認申請の要否」を明文化して、トラブル防止を図ります。
【新たに追加された「新2号建築物」とは?】
改正により「新2号建築物」という区分が新設されました。下記に該当する建物はリフォームに大きな影響を与えます。
新2号建築物の条件: 木造2階建以上の戸建住宅または木造平屋建で延床面積200㎡を超える建物
今まで、木造2階建以下・延床500㎡以下などの「4号建築物」は確認申請が不要でしたが、新2号建築物は確認申請免除の対象外となり、リフォームでも確認申請が必要になるケースが増えました。
★建築確認申請が必要となるリフォームの具体例
(以下のような工事では申請が必要です)
• フルリフォーム・スケルトンリフォーム
内部をすべて解体し、構造部分に手を加える大規模工事。
• 主要構造部の改修
柱・梁・耐力壁など、建物の強度に関わる部分を変更する場合。
• 過半基準を超える修繕・模様替え
建物の床面積の過半に及ぶ工事は「大規模修繕」とみなされます。
• 増築・用途変更を伴う工事
住宅を店舗に改装するなど、用途変更を含む場合も確認申請が必要です。
★建築確認申請が不要なリフォーム
(以下のような工事は申請が不要です)
• 内装の模様替え
クロス張替え、床材交換など
• 設備更新
キッチン・浴室などの交換
• 外壁塗装や屋根の葺き替え(構造に影響しない部分の場合)

【注意点】
確認申請が必要であるにも関わらず、確認申請をしないで工事を行う違反者には、1年以下の拘禁刑(2025年6月1日から施行された改正刑法により、今までの懲役刑と禁固刑が一本化されました)又は100万円以下の罰金となります。
◎建築確認又は完了検査を申請しなかった建築主
◎確認済証の交付を受けずに工事を行った工事施工者
また、今後は確認申請をしていない建物は売却が困難になることも考えられます。

【まとめ】
- 2025年4月の建築基準法改正で「新2号建築物」が追加され、木造2階建て住宅などでもリフォーム時に確認申請が必要となるケースが増加します。
- 主要構造部に関わる工事や過半を超える修繕は確認申請が必須です。
- 内装や設備更新など軽微な工事は確認申請不要です。
- 無申請の工事は法的リスクが大きいので、必ず専門家に相談してから計画を進めることが重要です。
お子様へ贈る 今月のおすすめ絵本(読物)


ぶんぶくちゃがま
文:望月 正子
絵:二俣 英五郎
出版社:世界文化社
昔々、ある所に正直な古道具屋のおじいさんがいました。ある日、おじいさんは、子供たちにいじめられていた狸を助けてあげました。おじいさんが家に戻ると助けた狸がやってきて、お礼をしたいと話しました。【お寺の和尚さんに売って、儲けて下さい】と狸は茶釜に化けました。
トウリハウジング特選物件情報
編集後記

2025年4月の建築基準法改正では、建築確認の審査がこれまで以上に厳格化されます。これにより、設計段階から法令適合性がより重視され、建築士や事業者に求められる範囲が広がってきています。特に影響が大きいのは、違反建築や再建築不可の戸建です。現在の状態が現行基準から大きく外れている場合、改修や用途変更のハードルが上がり、資産価値の見直しが必要になるケースも増えてきます。また、再建築不可物件では、建て替えを前提として考えることが難しいので、売買や活用方法の検討に慎重さが求められます。 一方で、既存不適格建築物については、一定の条件下で基準の適用が緩和される場合もあり、必ずしもすべてが不利になるわけではありません。建物ごとに状況が異なるため、専門家に相談しながら最適な対応策を検討することが必要になります。今回の改正は、建築物の安全性と省エネ性能の向上を目指す流れの一環であり、今後の不動産活用に大きな影響を与える改正です。